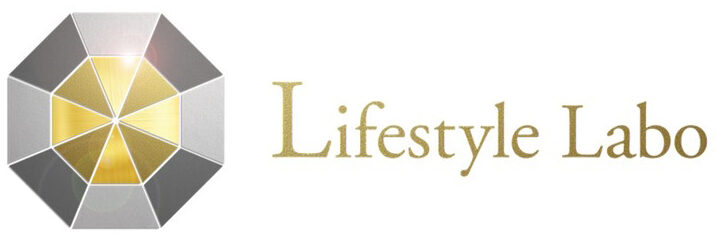「私が正しい。だから従って。」——そう言うつもりはなくても、つい子どもの舵を握ってしまう。
40〜60代の私たちは、家を守る責任も、人に迷惑をかけない常識も、体にしみ込んでいます。だからこそ、早く安全に進めたくて、「こうしなさい」「それはダメ」と先回りの声が出ます。けれど、その一言が、子どもの心のハンドルを少しずつ奪います。
まず、立ち止まって深呼吸。
目の前の子は「命令を待つ人」ではなく、「自分の考えを育てる途中の人」。そう見方を変えるだけで、会話がやさしくなります。
たとえば「宿題したくない」。
「やりなさい」ではなく、「そう感じる理由、教えて?」から始めます。疲れているのか、やり方がわからないのか、ただ休みたいのか。理由が見えれば、解き方を一緒に確認する、時間を区切る、今日は量を減らす、など小さな選択が作れます。子どもは「自分で決めた」感覚を得て、次は自分から動きやすくなります。
服や髪型でぶつかる日もあります。
「その格好は非常識」では、親の物差しだけが残ります。「どこに着ていく予定?相手は誰?何を大事にしたい?」と聞き、TPOと自己表現の両方を考えさせます。ルールを押しつけるより、自分で考える力が育ちます。
スマホ時間でも同じ。
取り上げれば一時停止はできますが、工夫は育ちません。「何に一番使う?何分なら気分がいい?」と具体的に聞き、家族のルールを一緒に作ります。決め方を体験した子は、外でも自分を整えやすくなります。
買い物の場面でも同じです。
親が全部選んで会計まで終えるより、「今日はあなたが一品選ぶ日。理由も教えて」と任せる。失敗してもOK。選び直しのコツを一緒に学べます。これが自己決定の小さな練習です。
「私と違う考え」を怖れないこと。
心がざわついたら、「私は心配しているだけ」と言葉にしてから、「あなたはどう考える?」と返す。親の感情を正直に見せつつ、主役は子どもの考えに戻すのがコツです。
最後に、合言葉を三つ。
1)まず聴く——理由を集める。
2)一緒に考える——選択肢を並べる。
3)小さく決める——今日できる一歩にする。
子どもは、親に管理されるほど動かなくなり、信じられるほど動き出します。
「言うことを聞かせる」より、「自分で動ける人に育てる」。そのスイッチを入れるのは、今日のあなたの一言です。