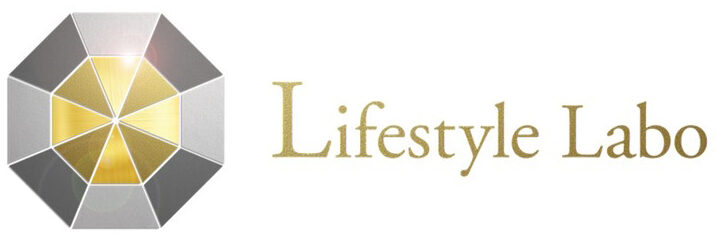「宿題、もうしたの?」「早くやりなさい!」
気がつけば、つい子どもに声を荒げてしまう——。
そんな自分に、あとで自己嫌悪することはありませんか?
多くのお母さんが、子どもに「ちゃんとしてほしい」「困らないようにしてあげたい」という優しさから、
つい先回りして指示を出してしまいがちです。
でも実はそれ、子どもの“自立”の芽を摘んでしまう行動かもしれません。
たとえば、ある小学生の男の子。
学校から帰ってきたあと、宿題をするタイミングについて、お母さんはこう尋ねました。
「今すぐする?それとも、ご飯を食べた後にする?」
すると彼は、「ご飯のあとにする」と自分で選択。
けれど実際は、ご飯の後に眠くなって「明日の朝する」と言って、そのまま寝てしまいました。
翌朝、案の定起きられず、宿題はできないまま登校。
先生に叱られて、家に帰るなり「お母さん、なんで起こしてくれなかったの!?」と責めるような口調。
——ここで、お母さんはどう対応するべきでしょうか?
多くの方は「だから言ったでしょ」と叱ってしまいそうになります。
ですが、この場面こそが、子どもに「自由」と「責任」の関係を教える絶好のチャンスなのです。
「自由」とは、好き勝手に振る舞っても許されることではありません。
自由に選ぶ権利があるからこそ、その選択の結果には“自分で責任を取る”必要があります。
これを「自己責任」といいます。
このような経験を通じて、
「自分の選択には結果が伴う」
「失敗しても、それは自分の学びのチャンスだ」
と気づけた子どもは、少しずつ自立していきます。
大切なのは、親が「代わりに責任を取ってしまわないこと」。
「可哀想だから…」とつい助けてしまえば、
子どもは「うまくいかなかったら誰かが何とかしてくれる」と思い込み、
自分で人生を切り拓く力が育ちません。
40〜60代のお母さん世代の多くは、「我慢してでも正しくしなさい」という教育を受けてきた世代です。
そのため、どうしても「失敗=悪いこと」と捉えがち。
でも今の時代は、失敗こそが“学び”の宝庫。
小さなうちに失敗し、「自分で何とかする力」を育むことが、将来の大きな自立につながります。
子どもを信じて任せてること。
そして、失敗したときにこそ「あなたの選択を尊重しているよ」という姿勢で見守ること。
この姿勢が、子どもの自立にとって何より大切なことなのです。